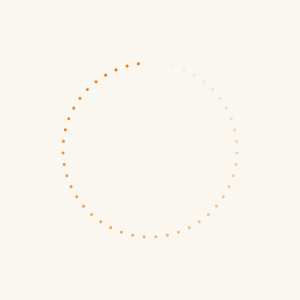
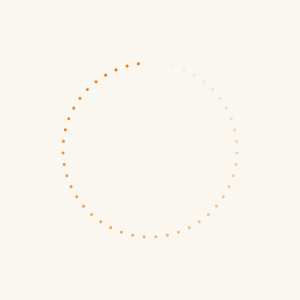
ビジョンという言葉は、さまざまな文脈で使われます。
個人が「こう生きたい」と願う未来像もビジョンなら、企業が掲げるミッションやパーパスもまたビジョンと呼ばれます。
組織という共同体の中では、この2つのビジョン──
すなわち「個人ビジョン」と「共同体ビジョン」──が交差する瞬間があります。
そして、その重なりの部分を「共有ビジョン」と呼びます。
ここでは、3つのビジョンを分けて考えてみます。
個人ビジョン:自分自身が何に価値を感じ、どんな未来を望んでいるかという内発的な指針
共同体ビジョン:会社やチームが掲げている理念・目的・存在意義
共有ビジョン:この2つが重なった領域。「この組織で、この自分として、生きたい」と感じられる場所
この共有ビジョンとしての重なりが大きく、かつ深いほど、人は自分のエネルギーを組織の中で活かそうとします。
ただし、「重なっている」といっても、その質や深さにはグラデーションがあります。
ここでは、個人ビジョンと共同体ビジョンの重なり具合を6段階で整理してみましょう。
① 重なりが何もない
自分のビジョンと組織のビジョンに接点がない状態です。
「ここでやりたいことはないけど、働いている」という割り切り。
指示待ち、惰性、または転職を視野に入れている状況です。
② 理解はしているが重ならない
組織ビジョンを理解し尊重はしているけれど、自分の価値観とは異なる場合です。
「いいことを言っているとは思うけど、自分のテーマではない」と感じる。
表面的な同調や、やや傍観者的な距離感があります。
③ 一部共感できるテーマがある
組織ビジョンの一部に共鳴できるものがある状態です。
「この部分は好き」「ここだけは自分の軸と重なる」など。
選択的な貢献や、役割を限定した関与になります。
④ 感覚的に共鳴している
言葉にしきれないけれど、「なんとなく分かる」「好きな雰囲気がある」と感じる状態です。
空気的な共鳴があり、感情的な温度も高め。
チームへの温かい姿勢や、暗黙の協力が生まれます。
⑤ 意識的に重なりを見出している
自分のビジョンの中に、組織ビジョンとの接点を自覚的に持っている状態です。
「私はここにこういう意図でいる」「この点が自分のビジョンと重なる」と説明できる。
自発的な行動や他者への発信、対話の積極性が見られます。
⑥ ほぼ完全に重なっている
組織ビジョンと自分のビジョンが深く一致している状態です。
「この組織でやりたいことが、そのまま自分のやりたいこと」という感覚。
高い当事者意識や推進力、他者を巻き込む力があり、
ビジョンのために組織も自分自身も変革できます。
こうして見ていくと、同じ組織にいて「共有ビジョンを持っている」とされる人たちにも、さまざまな段階があることが分かります。
「共有ビジョン」とは、単に“重なった部分”のことなのでしょうか?
重なりという考え方は、構造としてはとても分かりやすいものです。
けれど、それはあくまで状態を切り取った“スナップショット”にすぎません。
本当に重要なのは、その重なりがどのようにして生まれ、変化していくのかという“プロセス”ではないでしょうか。
実際のところ、共有ビジョンとは「誰かが定義した場所」に人が集まることではありません。
むしろ、人が集まり、対話をし、自分の想いを表現し、時にはぶつかり合いながら、少しずつ“できあがっていくもの”です。
つまり、共有ビジョンとは──
最初から“ある”のではなく、“共に育てるプロセス”の中で生成され続けるもの
なのです。
最初は、一人の想いから始まったビジョンだったかもしれません。
しかし、そこに共鳴が生まれ、誰かが自分の願いを重ね、さらに新しい観点が加わっていきます。
そうして少しずつ形を変えながら、個人と組織のあいだに“共に見る未来”が立ち現れてくるのです。
これが、私たちがビジョンという言葉を使うときに、「目指すべきビジョン」のあり方ではないでしょうか。
共有ビジョンを語るとき、私たちはつい「すでにあるもの」として話してしまいがちです。
けれど、本当に大切なのは、その生成のプロセスにこそあります。
個人のビジョンに耳を傾け、言葉にする時間を持ち、そこから再び組織のビジョンを見直していく。
そんな往復の中にこそ、「本当の意味での共有ビジョン」が育っていくのだと思います。
サービスの詳細については
下記ボタンよりGoogleフォームから
ご連絡ください。