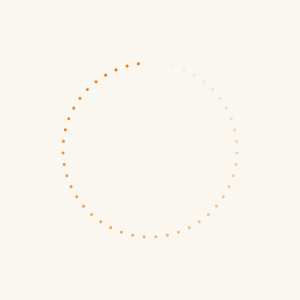
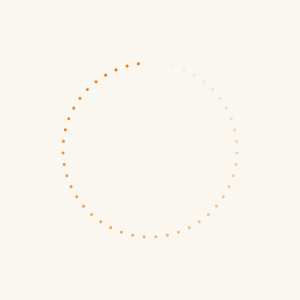
以前のブログで「技術的課題」と「適応課題」の話をしました。
「技術的課題」は「答えが(ある程度)わかっていて対応できる課題」、「適応課題」は「答えがはっきり示せず、状況に合わせて対応していく必要がある課題」です。今の世の中はVUCAの時代であり、複雑さと不確実性が増しているため、すぐに答えが出せない適応課題が増えているという話でした。 今回は、この話題をもう少し掘り下げてみようと思います。ひとつひとつは「技術的課題」に見えるのに、それが集まると「適応課題」になってしまう、という話です。
経営課題として「現場での在庫管理を改善しよう」となったとします。個別の課題をひとつひとつ把握しながら、解決していこうとする。
たとえば──
・エクセルでの在庫台帳を最新のクラウド型に切り替える
・入出庫のルールを明文化する
・バーコード管理を導入する
・定期棚卸のスケジュールを決める
どれも、「やろうと思えばできる」ことです。
それぞれは、明らかに技術的課題です。正解に近いものがあり、すでに導入事例も多く、どうやればいいかも見えている。
なのに、いざ全部をやろうとすると──「なぜか進まない」。
それは「技術的課題」が「適応課題」に変化した瞬間です。
ひとつの施策、たとえば「入出庫のルールを明文化する」だけなら、マニュアルを書いて、みんなに配布して、周知すれば終わりかもしれません。
でも、それにバーコード管理の導入が加わると、棚卸のやり方が変わり、クラウド台帳の入力ルールが変わり、入力する担当者が変わり、現場の動線や手順が変わる。
誰がどう関与し、どこで連携すればいいのかが、急に“個人の努力”では解決できない問題になるのです。
「どれもそれぞれやれるはずだったのに、組み合わせたら、うまくいかない」
これは、複数の技術的課題が集まることによって、「組織全体の適応課題」に発展した状態です。
技術的課題には“正解”があります。
でも、適応課題には“正解”がありません。どこかに答えがあるわけではなく、全員で手探りしながら最適なやり方を「見つけていく」必要があります。
先ほどの例でも、具体的な対応すべき課題も難しくなっていますが、「今の現場の空気感」「誰が発言しやすいか」「どこで疲弊感が出ているか」など、可視化されにくく、声に出されない課題も引き起こされてしまいます。
これらを無視して「技術的に正しいこと」を押し付けると、反発や疲弊が起きてしまう。
つまり「答えを知っている誰かが頑張れば解決する」という前提そのものが成立しません。そんな「答えを知っている誰か」が存在しえないのです。
組織が成長するときとは、要するに新しい案件が増えていくということです。新しいこと、その一つだけを見ればちょっとしたチャレンジがあるくらいで、なんとなくやり方はわかりそうに見えます。
でも、その「ちょっと」に対応するには現時点での技術が追い付いていいない。だから、学ぶための時間が欲しい。なのに、組織の中に人も少ないから、「掛け持ち」になってしまい、既存案件を回しながらの対応となる。
新しい案件の対応を試行錯誤しようとすると、既存案件にかけられる時間が減る。既存案件に時間をかければ、新しいことに対応する部分が場当たり的になる。結果的に、どちらにもほころびが出始めます。
担当者は本当に一生懸命やっているのに、混乱が玉突きになっていく。技術課題に近かったはずの問題が、リソースや連携、優先順位の問題を帯びてくる。そうすると、とたんに技術課題の「適応化」が始まります。
このような状況では「対話」が不可欠になります。
それぞれが見ている現場の景色、現実、違和感を出し合い、ひとつひとつ確認しながら前に進む。
そして、うまくいかなくても「うまくいかなかった理由」を学び、次に活かしていく。
この試行錯誤のプロセス自体が、組織としての“学習”です。
適応課題は、誰かの能力の問題ではなく、組織全体の対応力を問うものです。
だからこそ「みんなで少しずつ学ぶ」しかないのです。その学ぶべき対象は現場の担当者だけでなく、経営陣と呼ばれる人たちも含まれます。
経営陣の意思決定がどのように現場の混乱に関与しているか?その決定ひとつひとつは会社の成長のため、社会のニーズに応えるためかもしれませんが、現場が疲弊してしまっては、顧客に品質の良いサービスを提供することはままなりません。
・技術的課題の組み合わせが、適応課題に変化する
・全体での整合性が問われることで、個人のスキルや努力では解決できない領域に入る
・適応課題には正解がないため、対話と学習を通じて「見つけていく」しかない
「在庫管理のDX化」も、「会議のやり方改革」も、「働き方の見直し」も、「新規事業への対応」も、
どれも、部分だけを見れば“できること”ばかりです。
でも、それらを組み合わせていくと、組織全体に影響を与えるようになり話が変わってきます。
だからこそ、技術課題と適応課題という概念を理解し、ひとつひとつの案件がどちらの性質のものかを意識的に振り分ける。そして、技術課題も集まれば適応課題に発展してしまう構造があることを知っておく。「適応化」の影響を甘く見積もらず、みんなで対話しながら前に進む力を、今の組織は手に入れる必要があります。
弊社の提供する組織運営支援サービス「さいくる」は課題の「適応化」を前提とした、組織全体の対話力に伴走する設計となっています。もし、組織運営に苦慮していることがありましたら、いつでもご連絡ください。一緒に考えながら進めましょう。
サービスの詳細については
下記ボタンよりGoogleフォームから
ご連絡ください。