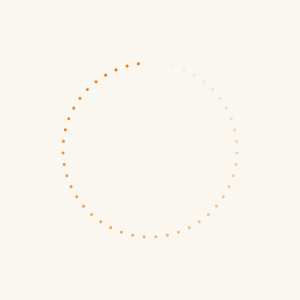
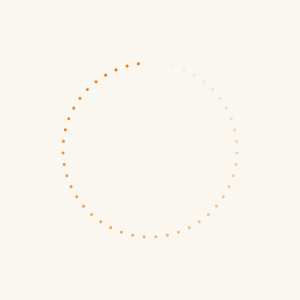
私たち人類はなぜ言葉を手にしたのでしょうか?なぜ、言葉を持ち、他者とコミュニケーションをする必要が生まれたのでしょうか?
ひとつの仮説としては、「野生の中で生き残るため」だったと言われています。
外敵の情報を仲間に伝えるため、
危険な植物や動物を教え合うため、
そして、子どもたちに知恵や技術を伝えるため。
言葉は「生き延びるための道具」として、人類の進化の過程で磨かれてきました。
そして、言葉は「つながり」、「協力し合うため」に生まれたと言えると思います。
しかしながら、現代の私たちは、
野生の脅威も、飢えも、直接的な危険もほとんど経験せずに暮らしています。
スーパーマーケットには食べ物があり、交通機関は整い、病院もあります。
かつて命を守るために必須だった言葉は、
その“必要性”を失い、ある意味で「余っている」状態になっているんだと思います。
そして、余剰となった言葉は、ときに人を傷つけるためにも使われるようになりました。
SNSでの誹謗中傷や、マウント、切り取り、論破。
本来は助け合うためにあったはずの言葉が、
争いや分断を生む道具として使われる──
それが、現代の一つの現実の側面です。
ただ、一方では、人類は言葉を遊戯的にも、創造的にも発達させてきました。
物語、詩、哲学、芸術、ユーモア、祈り。
言葉は単なる道具を超えて、私たちの「心」を豊かにし、「世界の物語」を紡ぐものに昇華させました。
そして、あらためて現代に目を向けると「地球環境問題」という、人類全体に共通する新たな「見えにくい脅威」が現れつつあります。気候変動、資源の枯渇、生物多様性の損失、世代を超える課題。
このような問題は、一人で解決することはできません。
誰かを責めるのではなく、共に考え、選び直し、行動する必要があります。
このような脅威こそが、もう一度言葉に”必要性”という力を与えるかもしれません。
我々が「つながるため」には必ず言葉が必要だからです。
弊社は「対話」による組織づくり支援にこだわっています。
対話とは、相手を論破することでも、ただ情報をやりとりすることでもありません。
「あなたから見えている世界を、私も見えるようになりたい」
「あなたが大切にしていることを、私は知りたい」
そんな姿勢で交わされる言葉のやりとりです。
相手を知ろうとして、より深く、その言葉の前提や背景に潜り込んでいく。
そのために使われる言葉。
それは、人類が進化させてきた言語の最も深く、最も大切にする使い方なのかもしれない。
そのように考えたら、日々仕事で関わる仲間と対話を始めることは、環境問題をはじめとする人類共通の課題に対処する力をつけることに、つながっているともいえるのではないでしょうか?
私たち人には選ぶ力があります。
「選択できる能力を自覚すること」こそが「自由」の意味です。
言葉を、つながりのために使うのか、それとも分断のために使うのか。
共に成長するために使うのか、他者を排除、非難するために使うのか。
もし私たちが、対話のスキルを育て、対話の場をつくり、共に分かち合う文化を育てていくことができたなら──遠い昔に、人類が生き残るために言葉を持ったという原点に、もう一度帰ることになるのかもしれません。
サービスの詳細については
下記ボタンよりGoogleフォームから
ご連絡ください。