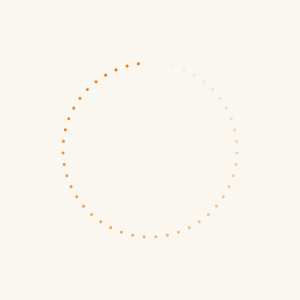
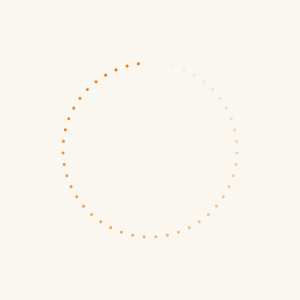
何よりも成果が重要だ。これはよく聞かれる言葉です。役員も組織リーダーも、相手に成果を求めます。
「営利企業だから」、「どこから給料が出るのか」、そう言われると「それはそうだよな」と納得する人も多いと思います。
食っていくためには必要だよね、その論理は反論の余地が少ないように思えます。
でも、一方で皆さんは感じているのではないでしょうか?
「そうやって『成果、成果』と言われるから気持ちが萎える…」
「いつもプレッシャーにさらされ、ストレスが強い」
上司はこちらを管理しチェックする人であり、相談する相手ではない。
同僚はが成果を出し評価があがると、相対的に自分の評価は下がる。
最初は仲の良かった同僚も、月日とともに、「成果を競う相手」へと「関係」が変化していく。
そして組織の中で気の許せる相手は減っていき、ストレスのかかる時間だけは増えていく。じゃあ、プライベートを優先しようと思うけど、有給はとりにくい雰囲気がある。そういうことが続くと次第に「何のために働いているのか?」なんていう「思考」が生まれる。
後ろ向きの思考になりたいわけじゃないけど、どうしてもモチベーションがあがらない。「もっと積極的に動け」なんて言われるけど、ハツラツと動くのは難しく、なんとかやれることをやる。そんな「行動」が精いっぱい。
結果的に、成果もイマイチだったりする。成果が大事なことはわかっているんだけど…。そしてまた、「成果が足りない」と指摘されるサイクルへ。
組織論の研究者ダニエル・キムは組織における「成功の循環モデル」を提唱しました。
そこでは「悪循環」「好循環」が定義されており、「成果」から始めるのは「悪循環に陥る」と定義しています。
<悪循環>
成果の質→関係性の質→思考の質→行動の質
成果を先に求めるから関係性の質が下がり、思考の質がネガティブになり、行動に積極さが失われる。
そして成果が出にくくなる。成果が出てないからますます成果を求める圧力が強くなる。
一方、好循環は、次の順番で生まれるといいます。
<好循環>
関係性の質→思考の質→行動の質→成果の質
いい関係性があると、思考が前向きになりアイデアが出やすくなり、いい関係性とアイデアがあれば、失敗を恐れず前向きで協働的な行動が増え、成果もあがりやすくなる。仮に成果が不十分でも関係性が良いから、共に失敗から学び、改善策や次のアイデアを考えて進める。
このモデルをどう思いますか?
弊社は全面的に賛成の立場です。
では、関係性はどうすれば良くなるのか?
その答えは「対話」にあります。
人と人が、何を思い、何に戻り、何を大切にしているのかを聞き合うこと。ただ伝えるだけでも、説得することだけでもない。言葉の表面上の意味でだけではなく、その言葉の奥にある背景や意図を把握しようとすること。
これは聞く側がそのように聞けばいいだけではなく、話す側も積極的に開示する必要もあります。
対話は、どちらか片方ではなく「対」で行う行為であり、「対」で作り上げる「話」です。
それらを続けるうちに、語られないもの存在、違和感、に敏感になり、まだ言葉にならない途中段階の考えを、受入れ、共に大切にしようとする姿勢が生まれます。
組織の中で、そのような姿勢で行われる対話が増えていけば、関係性が良くなります。
いわゆる「心理的安全性」が高い組織へと変容していきます。
関係性作りの起点は「対話」です。
成果に目が行きそうになるとき、組織が振り返るべきは、いつも「関係性」です。
指示的なコミュニケーション、上意下達の意志決定は「速さ」があります。スピード重視の世の中においては、それが一般的です。一方で対話は時間がかかります。簡単に答えは出ません。でも、本当に長期的な成果を望むなら、急がばまわれ。コミュニケーションにおける「対話の比率」を上げていきましょう。
サービスの詳細については
下記ボタンよりGoogleフォームから
ご連絡ください。