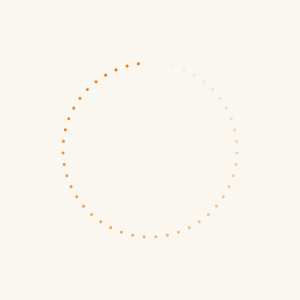
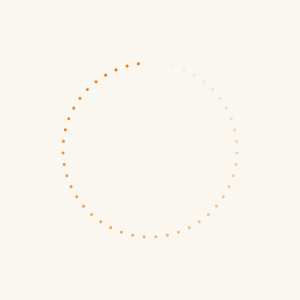
対話とは、単に言葉をやりとりすることではありません。
対話とは、言葉の背後にある意図、想い、価値観、さらにはその人自身の見ている世界を探り、分かり合おうとする共同作業です。
目的は説得や約束ではなく、「分かり合い」であり「相互理解」にあります。
たとえ意見が異なる場合でも、相手の考えや視点を認める。最終的な結論に納得はできなくとも、その意図や立場には理解ができる。そういった位置からお互いを見ることで、新しい気づきや理解が生まれる。
しっかりと土台を共有した上で会話を進める。これが対話の本質です。
しかし、対話が必要というと、人はつい自らのことを話そうとしています。
どう伝えるか。どう説明するか。なんとか意図を伝えようと長々と説明をする。
そのこと自体は悪くないのですが、対話の本質は話すことではなく、実は「聞くこと」にあります。
相手の言葉の意図や背景を探ろうとする。表面的な言葉の意味だけではなく、その背後にある想いや本心を探る。
そのためには、聴く姿勢、聴く意識、そしてより深く思考を促すための問いを投げかける。
よりよい対話には、それぞれが「上手な聞き手になること」が求められます。
上手な聞き手といえば、カウンセラーを思い浮かべるかもしれません。
カウンセラーはただ思いついたことを、自由に聞いているのではありません。しっかりとした理論や構造的で体系立てられた聞き方をしています。
カウンセラーがクライアントの話を受け止め、深めていくために用いる基本技法として主だったところで、下記のようなものがあります。
あいづち
クライアントの話のペースに合わせて、うなづいたり、「うんうん」「そうなんですね」とあいづちをうつ。
オウム返し
クライアントの言葉をほぼそのまま、少し短く繰り返す。
「私は辛いんです」→「辛いのですね」
開かれた質問
YES/NOで答えられる「閉じた質問」ではなく、5W1Hのような質問を投げかけ、相手の自由な語りを促す。
「どんな時にそう感じますか?」「そのとき、どんな考えが浮かびましたか?」
伝え返し(言い換え)
クライアントの感情や意図を汲み取って、カウンセラーの言葉に直して返す。
「いつも一人で寂しい気持ちになるんです」→「孤独だと感じているんですね」「誰か側にいて欲しい気持ちがあるんですね」
要約
クライアントの話をある程度聞いたところで、全体像を整理し、まとめて伝える。
仕事と家庭の両立の辛さを一連聞いた後で、「つまり、仕事のことも家庭のことも、どちらも今重なっていて負担が大きいんですね」
感情の明確化
クライアントが曖昧にしている感情を明確にするよう促す。
「それは怒りというよりも、悲しみに近いのでしょうか?」「あなたの言葉からは相手への不満を感じるのですが、私の理解はあっていますか?」
ここにに並べた技法は基本的に関係が浅いうちは上の方を使い、ある程度信頼関係ができたところで、より下側の技法を使い、関係を深めていきます。
カール・ロジャーズは「来談者中心療法」を創始し、現代のカウンセリングに大きな影響を与え、カウンセリングの父と呼ばれています。
このロジャーズが、カウンセリングの基盤となる「態度」として3つの原則を提示しています。先ほど述べた技法以前に、これがベースにないとカウンセリングが成立しないと言われています。
無条件の肯定的関心
クライアントの話す内容を価値判断せず、そのまま受け止める態度。
共感的理解
クライアントの感情や体験を、まるで自分のことのように感じ取り、正確に理解しようとする姿勢。
自己一致
カウンセラー自身が偽らず、ありのままの自己を保ちながらクライアントと向き合うこと。
対話は聞くことに本質がある。だから聞くプロのカウンセラーの技術について触れました。でも、普段の組織における対話でここまでのことを全部理解する必要はありません。
結局のところ突き詰めると、「信頼関係」が最も重要です。
相手の話を聞く意思があることは「相手の目を見て、しっかりうなづきながら、最後まで聞く」だけで伝わります。
相手の言葉をそのまま使うことを意識して伝え返すだけで、相手は伝わっているなと感じます。
もしよくわからない話だったとしても「こういう理解であってるかな」と確認してみれば、理解しようとする姿勢が伝わります。
仕事上の会話において、何か説明しようとしたときに「うんうん」とうなずいてもらう前に、「それはこうすればいいよ」と結論を言われてしまったり、なんだかしかめっ面で聞かれると「聞きたくないんだな」と思ってしまうと思います。そういうことをしないだけで十分なんです。
話す、聞くという行為は、人は誰しもが小さな頃から無意識に行うものですが、「ちゃんと聞こう」とするならそこには奥深いものがあるんだなと知っておくことです。
そしてなにより、自分自身がしっかり聞いてもらう経験を得ること。聞いてもらっているうちに、上述したような技術が自然と自分の中にしみこみ、他の誰かに使えるようになります。
そこではちょっと専門家の力を借りてみるのはどうでしょうか?
子どもが言葉を覚えるのと同じで、意識的に聞かれる経験を重ねるうちに自然とできるようになります。
意識の高い誰か一人だけが聞くを学ぶのではなく、組織の全員が同時多発的に「聞かれる」を体験する方が効率よく組織全体での聞く力、対話力が上がっていきます。
サービスの詳細については
下記ボタンよりGoogleフォームから
ご連絡ください。