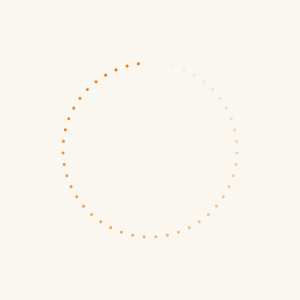
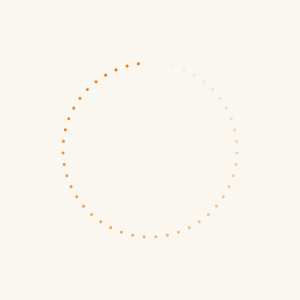
組織づくりの現場では、「対話が大切だ」と言われる機会が増えています。特に「1on1が重要」とされることも増えてきた印象ですが、「実際には何をすればいいのか?」「雑談と何が違うのか?」と思う人も多いと思います。
弊社が関心を持っているのは、対話をただのコミュニケーション手法としてではなく、「人が学び、変化するプロセス」を「促進する営み」として捉えることです。そして、その背景にはいくつかの理論的支柱があります。
今回は弊社が土台とする理論の中から、対話を「学習と発達の促進装置」として位置づけるための、3つの理論を紹介します。
最初に紹介したいのは、コルブ(David Kolb)の経験学習モデルです。このモデルでは、人の学びは「具体的経験」→「内省的観察」→「抽象的概念化」→「能動的実践」という4つのサイクルで進むとされます。
この循環の中で、特に内省(Reflective Observation)は、自己の経験を“意味のあるもの”として捉え直す重要なプロセスです。ここで対話が大きな力を発揮します。
他者との対話を通じて、自分の経験を語ることは、単に出来事を整理する以上の意味を持ちます。相手の問いや共感、視点の違いを受け取りながら語ることで、「自分では見えなかった意味」が浮かび上がってくる可能性が上がるからです。
対話は経験学習サイクルにおける”内省の触媒”といえます。 意識の高い人は内省を自分で始めることができますが、多くの人はそうではありません。それが普通です。何事でも何かを始め、継続するには誰かと一緒にやることが効果的です。内省も同じです。ひとりより誰かと一緒に進める方がうまくいきます。
フロイトなどの理論によると、私たちの意識は、一枚のフラットな層ではなく、いくつかの階層構造を持っています。
もっとも表面にあるのが「顕在意識」で、これは今この瞬間、自分が自覚的に捉え、言葉にできる領域です。
一方で、深く自覚されていない「無意識」も存在しており、そこには過去の経験、抑圧された感情、自動的な反応パターンなど、私たちの行動や思考に密かに影響を与えるさまざまな要素が含まれています。無意識に沈んでいたものも何かのきっかけで、ふと顕在意識に上がってくることもあります。
そして、この「顕在意識」と「無意識」の間に位置するのが「前意識」と呼ばれる領域です。前意識とは、「今この瞬間には意識していないが、注意を向ければ思い出せる」「ある程度の文脈や問いかけによって浮かび上がる」思考や感覚の層です。経験した直後に振り返れば、顕在意識や前意識に具体的経験を通じて得た多くの感覚にアクセスできます。
前意識や無意識へのアクセスは自分で深く考え実現することもできますが、誰かとの対話の中でも同様に起こります。特に、心理的に安心できる関係性の中で、適切な問いを投げかけられると、
「あ、今こう言葉にしてみて思い出したのですが……」
そんな気付きの瞬間が生まれやすくなります。 このように、対話はより深い意識へのアクセスを促し、自分でもまだ気づいていなかった思考や感情を意識するきっかけとなります。
3つ目は、発達心理学者ヴィゴツキーの「発達の最近接領域(ZPD:Zone of Proximal Development)」です。
ZPDとは、「今は一人でできないが、他者の支援があればできる領域」のこと。人は、自力で到達できるレベルだけでなく、「関係性の中でちょっと上の力を発揮できる」領域で成長していく、という考え方です。ひとりでは解けない問題も、先生に教えてもらえばわかった。そんな経験は誰しもにあると思います。でも、あまりに難しいといくら教えてもらってもわからない。この教えてもらえばわかる領域がZPDです。
このZPDを効果的に働く場とするのに、対話は非常に効果的な手段です。問いかけ、気づき、整理、確認といった対話の営みが、人の“今ここ”から、“他者の支援があるからこそ踏み出せる次のステップ”を引き出してくれます。コルブの学習サイクルの「抽象的概念化」の段階でうまくこの領域を意識した関わりができれば、より多くの学びが形になります。
ここまで見てきたように、対話とは単なる雑談や意見交換ではありません。
それは、
“学びと発達のプロセス”を支える本質的な営みです。 そして、それがうまく働くためには、話す内容だけでなく、「問いかけ」「傾聴」「信頼関係」「共に構造を見ようとする姿勢」といった対話の“あり方”が問われます。
組織であっても個人であっても、真の変化や学習は、対話という関係性のなかから生まれます。もしあなたが組織の変化を願っているなら、まずは仲間と「一緒に問いを持つ」ことから始めてみてはいかがでしょうか。その一歩は、相手だけでなく、自分自身の変化と成長も促します。
弊社は対話が生み出す関係性の価値を探求することを「リレーション・インクワイアリ― = 関係性探求」と呼び、「学習サイクル」を対話で支援することに特化した組織運営支援サービス「さいくる」を提供しています。もし興味があればぜひ、ご連絡いただければ幸いです。
サービスの詳細については
下記ボタンよりGoogleフォームから
ご連絡ください。